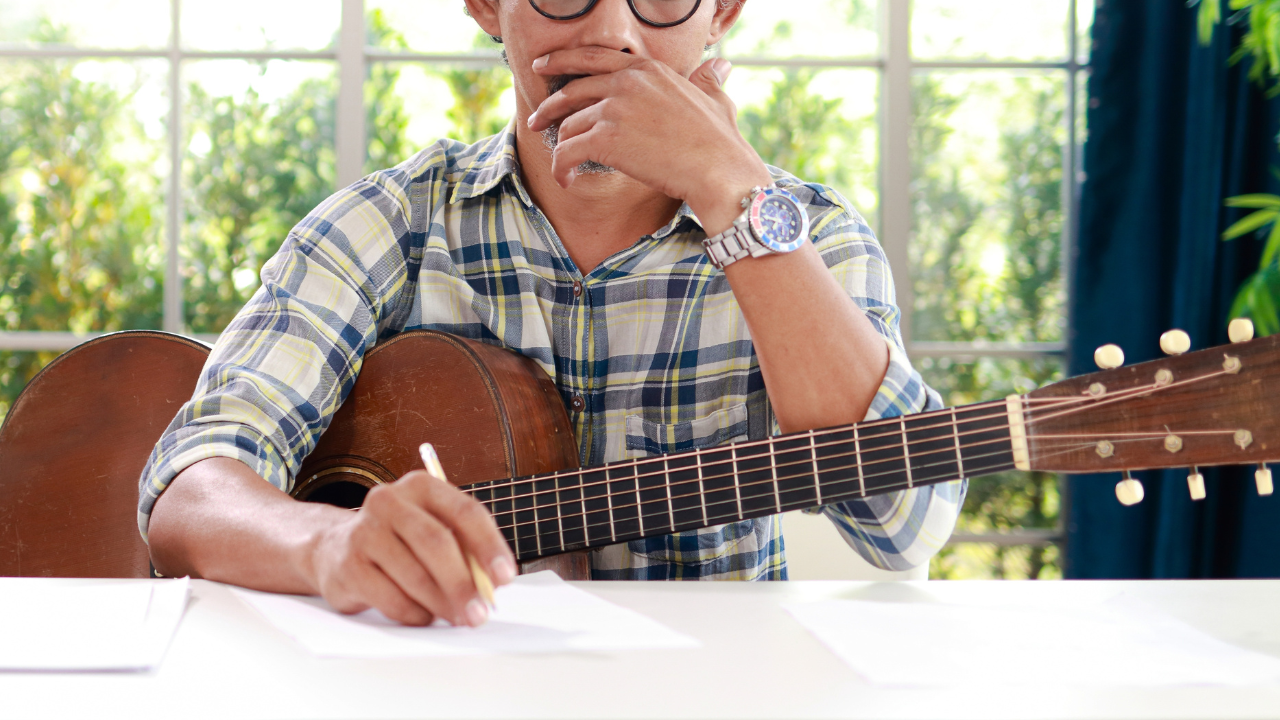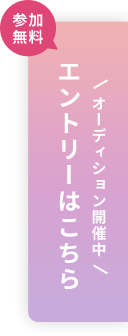音楽が好きな方のなかには「自分でも作曲してみたい」と思ったことがある方も多いでしょう。
作曲は難しいと思われがちですが、初心者でも必要な機材やソフトをそろえ、基本的なステップを踏めば、誰でもオリジナル曲を作ることができます。
この記事では、作曲に必要なものや初心者向けの作り方、押さえておきたいポイントを解説します。音楽制作を学びたい方や、自分だけの曲を作ってみたい方は、参考にしてください。
作曲とは?

作曲とは、音楽を創り出す作業のことで、主にメロディー・歌詞・コードという3つの要素から構成されます。
曲の主旋律となるメロディーに物語や感情、伝えたい言葉を歌詞にして、楽曲の土台となる和音(コード)をつなげて曲にします。
作曲には特別な才能や資格が必要なわけではなく、基本を理解しながら順序立てて考えることで、自分だけの音楽を創作できるでしょう。
初心者でもできる?
作曲は初心者でも始められます。最初は知識がなくても、スマートフォンやパソコン、楽器があれば感覚的にメロディーや歌詞を考えることができます。
現代では作曲支援アプリや無料のDAW(音楽制作ソフト)も豊富にあり直感的に操作できるため、誰でも気軽に作曲を体験できます。
大切なのは完璧を目指すのではなく、まずは楽しみながら音を組み合わせることです。
楽しみながら作曲を繰り返すことで自然とスキルも高められるでしょう。
作曲に必要な機材・ソフトウェア

作曲を始めるにあたって、特に高価な機材をそろえる必要はありませんが、最低限のツールがあるとスムーズに制作を進められます。
ここでは、作曲に役立つ基本的な道具やソフトを紹介します。
パソコン・スマホ
パソコンやスマートフォンは、作曲をするうえで重要なツールです。
特にパソコンは多機能なDAWを使うために必要で、曲のクオリティを高めたり編集したりする際に便利です。
一方、スマートフォンは気軽にアイデアを記録したり、アプリで簡単な作曲をするのに役立ちます。場所を選ばずに作業できることもあり、初心者には特に扱いやすいデバイスと言えるでしょう。
ピアノ・ギター
ピアノ・ギターなどの楽器は、メロディーやコード進行を作る際に役立ちます。
ピアノは鍵盤で音の関係性を視覚的に捉えやすい、ギターは持ち運びしやすく直感的にコードを押さえられるなど、それぞれの利点があります。
演奏スキルがなくても、基本的な和音やコードを鳴らせれば作曲に十分活用できるでしょう。
作曲アプリ
初心者におすすめなのが、スマートフォンやタブレットで使える作曲アプリです。
コード進行の提案やメロディー入力、録音機能など、便利な機能がまとまっており、直感的に操作できます。
GarageBandやマエストロ、Music Maker JAMなどは特に人気があり、音楽の知識や基礎スキルを身に付けながら作曲できるでしょう。
DAW(ソフトウェア)
DAW(Digital Audio Workstation)は、作曲や録音、編集、ミキシングを行うソフトウェアで、パソコンで本格的な音楽制作をする際に必要です。
DAWを使った音楽制作はDTM(デスクトップミュージック)とも呼ばれ、プロ・アマ問わず普及しています。
いずれは本格的な曲を作りたい、プロの作曲家やミュージシャンを目指したいという方は、取り入れてみると良いでしょう。
【初心者向け】作曲のやり方

未経験から作曲を始めるには、段階的に進めていくことが大切です。
まずは曲のテーマを決め、歌詞やメロディーの土台を作っていきましょう。順を追って考えることで、慣れていなくても曲作りの流れを理解できるようになります。
ここでは、初心者向けの作曲のやり方を紹介します。
ステップ1:曲のテーマを決める
作曲の第一歩は、曲のテーマを決めることです。
どんなメッセージを伝えたいのか、自分はどのような題材の曲を作りたいのかを考えましょう。
恋愛や人生観、家族・友人への想い、実現したいことなど、自分の体験や希望、伝えたいことを軸にテーマを設定すると、歌詞やメロディーの方向性が定まりやすくなります。
ステップ2:歌詞のキラーワードを考える
印象的なフレーズや感情を表す言葉を探し、聞き手の印象に残るキーワードを取り入れましょう。
シンプルで短い言葉のほうがメロディーを付けやすくなります。キラーワードがなかなか思いつかない場合は、好きなアーティストの曲からヒントを得るのも効果的です。
ステップ3:サビのシチュエーションを考える
曲の盛り上がり部分であるサビには、印象に残る情景や感情を描くと効果的です。
聴き手が曲の世界観に浸れるような、テーマを自分ごととして捉えられるようなシチュエーションを考え、歌詞を考えると良いでしょう。
ステップ4:シーンが明確になるよう歌詞を補足する
キラーワードや伝えたいこと、サビのシチュエーションなど、曲のメッセージをより明確に伝えるには、シーンが分かりやすくなる歌詞にすることが大切です。
特に5W1H(いつ・誰が・どこで・何を・なぜ・どのように)を意識して歌詞を補足することで、聞き手に伝わりやすく、情景が浮かびやすい曲になります。
ステップ5:コードを探す
曲のテーマやメロディーに合わせてコードを選びます。
明るく楽しげな印象を与えるメジャーコードと切なさや落ち着いた印象を与えるマイナーコードがあり、曲の出だしのコードはテーマに沿ったものを選ぶのがおすすめです。
ステップ6:曲の雰囲気に合わせてコード進行を考える
コード進行とは、曲の中でコードをどの順番で並べるかを決めて、いくつかのコードのまとまりを作ることです。
コード進行によって、曲の印象や与える感情の流れが大きく変わるため、テーマや歌詞に合った進行を選びましょう。
コードの組み合わせは多様にありますが、初心者は定番と言われるコード進行から選ぶのがおすすめです。
ステップ7:メロディーを決める
最後にメロディーを作ります。最初にサビから作ったり、歌詞を見ながら鼻歌を歌ったり、自分に合う方法でメロディーを考えてみましょう。
自然に口ずさめるメロディーを意識すると、印象的な曲に仕上がります。
作曲をする際に押さえておきたいポイント

初心者がスムーズに作曲を進めるためには、いくつかのポイントを意識することが大切です。
音楽理論の基礎を知ることや、作りやすいパートから始める工夫、ほかのアーティストの楽曲を参考にする姿勢が、完成度の高い作品作りにつながります。
以下で具体的なコツを紹介します。
音楽理論などの基礎を学ぶ
作曲において音楽理論の基礎を理解していると、コード進行やメロディー作りがスムーズになり、コード選択の幅も広がります。
スケール(音階)やキー(調)、コードの構造を知ることで、音の選び方に根拠が生まれ、耳になじみ印象に残りやすい良い曲を作れるようになるでしょう。
初心者でも、基本的な理論を学ぶだけで十分な効果が期待できます。
サビを最初に作る
サビは曲の中で最も印象に残るパートであり、聞き手の心をつかむ重要な部分です。
そのため、最初にサビを作ることで曲全体の方向性が明確になります。
メロディーや歌詞に一番力を入れたいサビの部分から作曲を始めると、ほかのパートにも統一感が生まれやすくなるでしょう。
アーティストのコードを真似する
作曲に慣れていないうちは、好きなアーティストの曲を参考にするのが効果的です。
特に、作りたい曲に近い雰囲気の曲のコード進行を分析し、似たパターンを取り入れたり、自分なりのアレンジを加えたりすると良いでしょう。
まずはワンフレーズを作る
最初から全体を完成させようとせず、まずは印象的な1フレーズまたは1コーラスを作ることを目指しましょう。
そのワンフレーズをもとに、AメロやBメロへと発展させていくのが効率的です。ひらめきを大切にし、録音やメモを活用してアイデアを逃さないようにしましょう。
音楽制作や曲の作り方を学ぶならテアトルアカデミー

趣味で作曲を始めてみたい方はもちろん、本格的に作曲や音楽制作を学びたい方は、テアトルアカデミーの「ON-LABO」がおすすめです。
音楽理論や作詞・作曲の方法、DTM、楽器の使い方など、実践的なカリキュラムが充実しており、作曲未経験者でも安心して学べます。
講師陣は全員音楽業界で活躍するプロのため、効率的なスキルアップが目指せるでしょう。
ON-LABOには、中学生から30歳までを対象とした「ON-LABO」と、31歳以上を対象にした「MUSIC100」があり、一人ひとりのレベルや年齢に応じたレッスンが受けられます。
テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!
- 実力派の役者が所属する芸能事務所に入りたい
- 大手メディアへの出演実績が豊富な芸能事務所に入りたい
- 芸能活動に向けた本格的なレッスンを受けたい
音楽制作を学んでオリジナル曲を作ろう!

作曲はパソコンやスマートフォン、楽器、DAWを活用すれば、アイデアを形にするのもスムーズです。
また、曲作りの流れを理解し、音楽理論の基礎やコード進行の知識を身に付けることで、より完成度の高い作品につながるでしょう。
作曲について本格的に学びたい方には、自宅にいながら作曲スキルを習得できるテアトルアカデミーのON-LABOがおすすめです。
ON-LABOに興味がある方は、まずは無料で受けられるオーディションにエントリーしてみてはいかがでしょうか。
テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!
- 実力派の役者が所属する芸能事務所に入りたい
- 大手メディアへの出演実績が豊富な芸能事務所に入りたい
- 芸能活動に向けた本格的なレッスンを受けたい