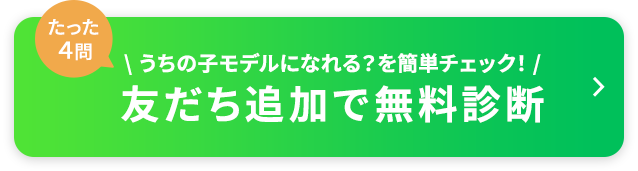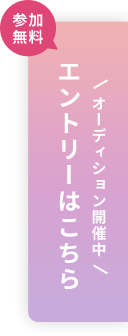赤ちゃんの成長のなかでも、つかまり立ちは歩き始めるまでのステップとして多くの保護者が楽しみにしている瞬間です。
しかし、「うちの子、つかまり立ちが遅いかも…」と心配になる保護者もいるのではないでしょうか。つかまり立ちを始める時期には大きな個人差があります。
この記事では、つかまり立ちの目安時期や練習方法、転倒対策について詳しく解説します。
赤ちゃんのつかまり立ちはいつから?

赤ちゃんがつかまり立ちを始める時期は一般的に生後8〜10ヶ月頃とされています。
しかし、子ども家庭庁の「令和5年乳幼児身体発育調査」によると、実際には大きな個人差があります。
早い子では生後5〜6ヶ月でつかまり立ちを始めることもあり、逆に11〜12ヶ月頃になってからようやく立ち上がる子も少なくありません。
この時期に幅があるのは、赤ちゃん一人ひとりの身体の発達や性格、日々の環境に左右されるためです。
そのため「ほかの子はもうつかまり立ちできているのに……」と焦る必要はありません。
赤ちゃんは自分のペースで着実に成長していきます。
保護者は安全な環境を整えつつ、赤ちゃんの成長を温かく見守ることが大切です。
ハイハイからつかまり立ち、歩くまでの成長過程

赤ちゃんは、歩くまでに首座りや寝返り、ハイハイ、つかまり立ちなどの成長過程があります。
それぞれの段階には前兆があり、少しずつ身体の準備が整っていくため、赤ちゃんの様子を注意深く見守ることが大切です。
ハイハイができるまで
赤ちゃんの運動発達は、まず首が座ることから始まります。
生後3~4ヶ月頃に首が安定し、続いて寝返りができるようになると、全身を使った動きの基礎ができ上がります。
生後6〜8ヶ月頃には腹ばいで手足を使い、ずりばいをする赤ちゃんも増えてくるでしょう。
そして体幹や腕、足の筋肉が十分に発達すると、四つん這いの姿勢が安定し、前進・後退ができるようになります。
これが「ハイハイ」です。ハイハイは生後10〜11ヶ月頃までにできる赤ちゃんが多いと言われています。
最初はゆっくりですが、次第にスピードが増し、動きも自在になっていくでしょう。
つかまり立ちができるまで
ハイハイが活発になると、赤ちゃんは次第に高い場所に興味を持ち始めます。家具や柵につかまろうとする動きが見られるのは、つかまり立ちの前兆です。
また、ハイハイのスピードが速くなったり、膝を伸ばして立とうとしたりするような動作が増えるのもサインの一つです。
これらの動きは、足や腰の筋肉が発達してきた証拠であり、身体を支える準備が整っていることを示しています。
赤ちゃんが何度も挑戦しながら徐々にバランスを取れるようになり、やがて安定したつかまり立ちができるようになるでしょう。
つかまり立ちから歩くまで
つかまり立ちができるようになると、赤ちゃんは「伝い歩き」へとステップアップします。
家具に手をかけながら横へ移動したり、方向転換をしたりして、少しずつ足を前に出す練習を繰り返します。
この段階ではまだ不安定なため転倒しやすいですが、筋力やバランス感覚の発達に役立つ重要なステップです。
つかまり立ちや、つかまったまま足を動かすことを何度も繰り返すことで、やがて手を放して数秒立てるようになり、次は1人で数歩踏み出す「よちよち歩き」へと進みます。
赤ちゃんが歩き始める時期は一般的に1〜1歳6ヶ月頃が多いと言われていますが、成長スピードは個人差があります。
赤ちゃんのつかまり立ちの練習方法

赤ちゃんは成長に伴って自然につかまり立ちを始めますが、歩行に慣らすために保護者が練習をサポートすることも効果的です。
安全に配慮しながら、遊び感覚で練習してみましょう。
保護者が脇を支えてサポートする
つかまり立ちを始める頃の赤ちゃんは、全身を支えるほどの筋肉が発達していません。
そのため、練習するときは、保護者が赤ちゃんの脇を支えて立ち上がる感覚をサポートするのがおすすめです。
赤ちゃんが自分の足に体重をかけられるようになることで、足腰の筋力が鍛えられ、立つ動作に慣れていきます。
最初は短時間で行い、少しずつ立っていられる時間を延ばしていくと効果的です。
赤ちゃんが楽しそうに取り組んでいるかを確認しながら行いましょう。
つかまりやすい家具を配置する
赤ちゃんが自分だけで立とうとする行動をしたら、つかまりやすい高さの家具を用意します。
例えば、安定感のあるソファやローテーブル、手すり代わりになる柵などがおすすめです。
赤ちゃんが安心して練習できるよう安定感のない家具は避け、角の尖った部分にはクッションを取り付けるなどして安全対策を行いましょう。
赤ちゃんが自分でつかまって立つ経験を繰り返すことで、赤ちゃんは少しずつ自信をつけ、バランス感覚を磨いていきます。
おもちゃを用意する
赤ちゃんが楽しく練習できるように、おもちゃを活用するのも効果的です。
例えば、つかまり立ちしたときに手を伸ばせる高さにお気に入りのおもちゃを置いてあげると、「取りたい!」という気持ちが自然と立ち上がる力につながります。
また、音が出るおもちゃやカラフルなおもちゃは赤ちゃんの興味を引きやすく、繰り返し挑戦する意欲を育てます。楽しさのなかで身体を動かすことでバランス感覚を養い、成長を促すことができます。
赤ちゃんのつかまり立ちには転倒対策を

つかまり立ちの時期は転倒やケガのリスクが高まります。
家庭内での工夫や安全対策をしっかり行い、安心して練習できる環境を整えてあげましょう。
危険なものを手の届く高さに置かない
つかまり立ちを始めると、赤ちゃんの行動範囲は一気に広がります。
そのため、お金やボタン電池、小さなおもちゃなど、誤飲の危険があるものは必ず片付けましょう。
また、飲み物や調味料なども手に取ってこぼす危険があるため、赤ちゃんの目線や手の届く高さに置かないことが重要です。
特にリビングやキッチンは危険物が多いので、日常的にチェックしておくと安心です。
何かをくわえていないか確認
赤ちゃんは好奇心から何でも口に入れてしまうため、つかまり立ちをしている最中に物をくわえていないか確認することも大切です。
もし口に物を入れたまま転倒すると、口内のケガや窒息の危険につながります。
おしゃぶりを口にしていたり、おもちゃを持っていたりする場合は一度やめさせ、何も持っていないことを確認してから練習させましょう。
日常的に「口の中は安全か」を意識して見守る習慣を身に付けておくことは赤ちゃんの安全を確保することにつながります。
コーナーガードや柵の設置
家具や壁の角は、つかまり立ちの赤ちゃんにとって頭をぶつけやすい危険ポイントです。
やわらかいコーナーガードを設置することで衝撃を和らげ、ケガのリスクを減らせます。
また、階段やキッチンなど立ち入ってほしくない場所にはベビーゲートや柵を設置しましょう。
赤ちゃんの行動範囲が広がる時期だからこそ、事前に環境を整えておくことが重要です。
マットを敷く
床にマットを敷いておくと、転倒した際の衝撃を吸収し、ケガを防ぎやすくなります。
特にフローリングやタイルは硬く滑りやすいため、クッション性のあるプレイマットを活用すると安心です。
防音効果もあるので、赤ちゃんが何度も立ち上がって転んでも音が響きにくいという利点もあります。赤ちゃんが安全につかまり立ちに挑戦できるスペースを作ることで、保護者も安心して練習させられるでしょう。
リュック型クッションや乳幼児用のヘルメットを用意する
後ろに転んで頭を打つことが多いつかまり立ち期には、リュック型クッションや乳幼児用のヘルメットも役立ちます。
軽量でやわらかい素材のものを選べば、赤ちゃんも嫌がらずに装着でき、転倒時の衝撃を和らげてくれます。
ただし、これらはあくまで補助的な安全対策であり、常に大人が見守ることが基本です。安全グッズを活用しつつ、赤ちゃんの挑戦をサポートしてあげましょう。
赤ちゃんの発達を伸ばすならテアトルアカデミー

赤ちゃんがつかまり立ちを経て自分の力だけで立ち上がるのは、運動能力だけでなく「自分で見たい」「触れたい」という知的好奇心の表れです。
これは自己表現の始まりであり、成長の大きな一歩と言えるでしょう。
赤ちゃんの可能性をさらに広げたいと考える保護者におすすめなのが、テアトルアカデミーのベビーコースです。
対象は0〜2歳6ヶ月頃までで、身体遊びや手遊び、読み聞かせ、歌など、年齢や発達段階に合わせたレッスンが行われています。
遊びながら学べる環境は、赤ちゃんの感性や表現力を育むのに最適です。
赤ちゃんの好奇心を刺激しながら親子で一緒に楽しめるレッスンが充実しており、成長を間近で見られるのも、テアトルアカデミーの特徴です。
テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!
- 鈴木福くんも0歳から所属!業界最大手の実績ある事務所で始めたい
- オムツモデルやテレビ出演など、豊富なチャンスが欲しい
- 芸能活動だけでなく、子どもの成長につながる知性や感性も磨いてあげたい
つかまり立ちが遅くても焦らないで!赤ちゃんの成長を見守ろう

つかまり立ちは赤ちゃんの成長において大切なステップですが、始める時期には大きな個人差があります。
赤ちゃんは自分のペースでしっかりと発達していくため、早い子もいればゆっくりと時間をかける子もいます。保護者は周りの子と比べずに焦らず赤ちゃんの成長を見守りましょう。
赤ちゃんの興味を育みながら身体の発達をサポートしたい方は、専門的な環境で表現力や知的好奇心を伸ばせるテアトルアカデミーのベビーコースがおすすめです。
赤ちゃんとの遊びや読み聞かせなど、育児に活かせる学びが多いため、保護者にとっても有意義な時間となるでしょう。
気になる方はぜひ、エントリーしてみてください。
テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!
- 鈴木福くんも0歳から所属!業界最大手の実績ある事務所で始めたい
- オムツモデルやテレビ出演など、豊富なチャンスが欲しい
- 芸能活動だけでなく、子どもの成長につながる知性や感性も磨いてあげたい