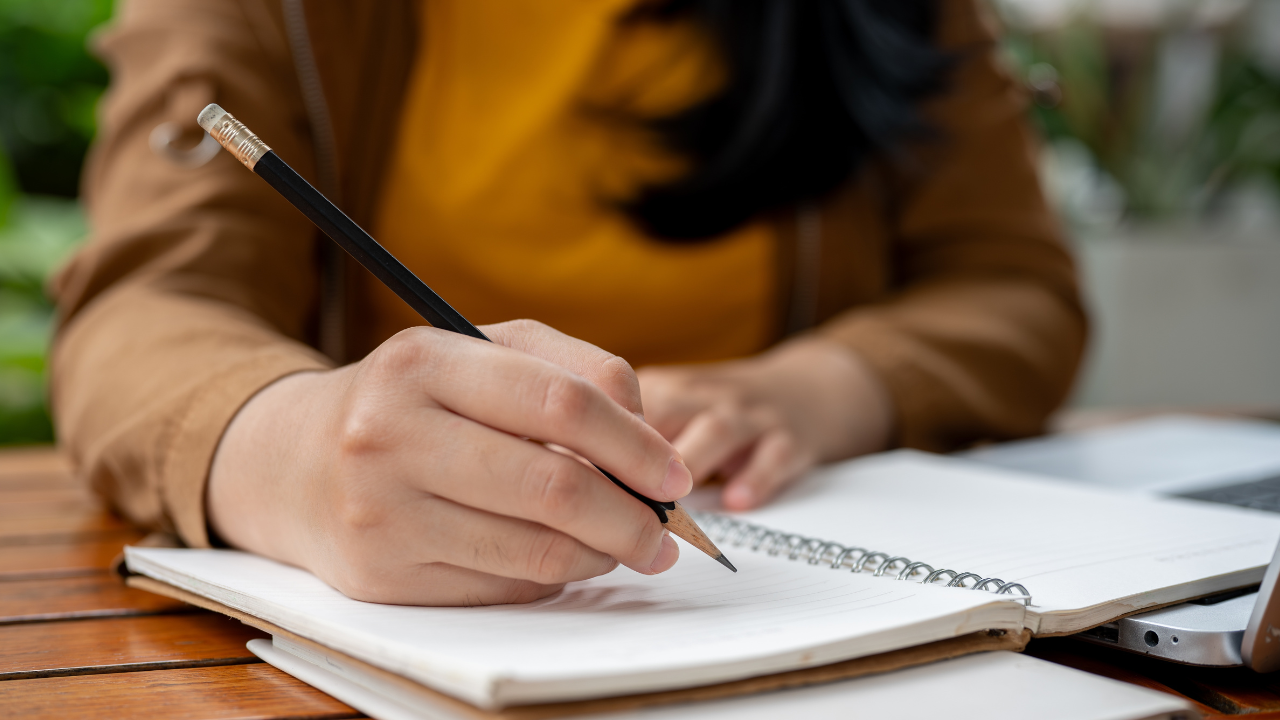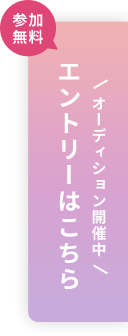「歌詞を書いてみたいけど、何から始めれば良いか分からない…」と悩んでいる方は多いかもしれません。作詞は特別な才能や高価な機材がなくても、誰でも気軽に始められる表現方法です。
この記事では、中学生でも挑戦できるようテーマの決め方から実際の書き方まで、一つひとつ分かりやすく紹介します。
【初心者向け】作詞のやり方は?
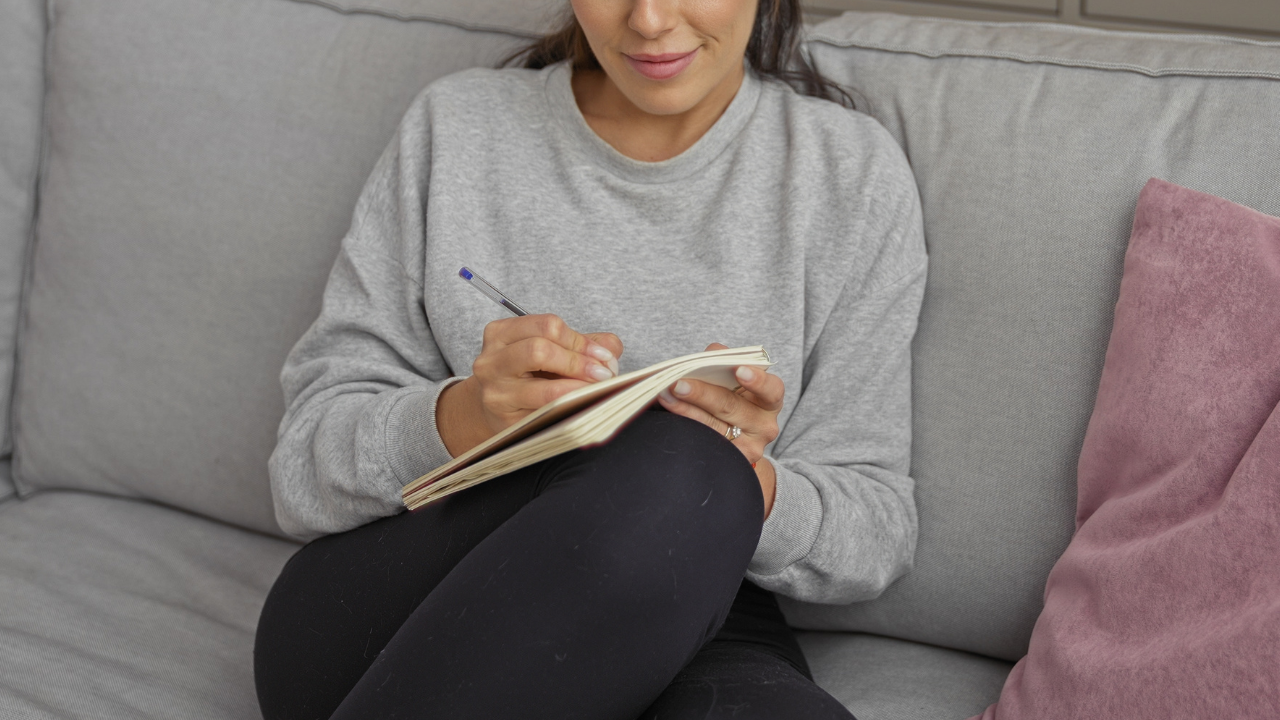
作詞はステップを踏めば、誰でも始められます。
ここでは、初心者でも迷わずに書き進められる5つのステップを紹介します。
①歌詞の「テーマ(何について歌うか)」を決める
作詞をするにあたって、最初に決めたいのが「テーマ」です。テーマは歌詞全体の軸となり、伝えたいことを明確にしてくれます。
また、テーマが決まっていれば、言葉選びや構成にも迷いにくくなるでしょう。
例えば、「今の自分の気持ち(楽しい・悔しい)」「学校生活での出来事(部活や放課後の思い出)」「空想の世界(物語の中の主人公)」などが一例です。
難しく考える必要はありません。「今、誰かに伝えたいことは何?」と自分に問いかけて、一番心に浮かぶことを選んでみましょう。
②物語の「設計図(構成)」を作る
テーマが決まったら、次は歌詞の流れを考える「設計図(構成)」を作ります。いきなり歌詞を書き始めると、ストーリーがブレたりメッセージを見失ったりするかもしれません。
そこで、5W1Hを意識しながら「誰が」「どんな状況で」「どう感じて」「どうなるのか」を簡単に書き出すと、物語の全体像が見えてきます。
例えば、以下のように箇条書きで書き出してみましょう。
- 試合に負けて落ち込んでいた自分が
- 友達の励ましで元気を取り戻し
- 次は絶対に勝とうと決意する
設計図があるだけで、歌詞の世界観が広がり、流れもスムーズになります。
③使いたい「言葉(キーワード)」を集める
テーマや構成ができたら、そこから連想される言葉を集めてみましょう。これは言わば、表現のための準備運動です。
例えばテーマが「夏の夕立」なら、「アスファルトの匂い」「濡れた前髪」「止んだ後の虹」「急ぎ足」など、思い付くままに書き出してみましょう。
五感(見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触る)を使って連想すると、よりリアルで印象的な言葉が見つかります。
具体的なキーワードを書き出しながらストーリーや情景を整理しておくと、作詞を書くのもスムーズになるでしょう。
④一番伝えたい「サビ」から書く
次は、曲の核となるサビから書いてみましょう。サビは曲のなかで最も印象的な部分であり、一番伝えたいメッセージを込める場所です。
サビがはっきりしていると、全体の歌詞にもまとまりが出てきます。ステップ3で集めたキーワードから特に心に残る言葉や普段のメモからインパクトのある言葉を選び、文章にしてみましょう。
文章は短くても構いません。「この気持ちを伝えたい!」というエッセンスをサビに凝縮させることが大切です。
⑤「Aメロ・Bメロ」で物語を肉付けしよう
サビが完成したら、次はAメロとBメロでストーリーを広げていきましょう。
Aメロでは状況や登場人物などを描写することで聴き手を物語に引き込み、Bメロは、サビに向かって感情を高めていく役割があります。
ステップ2の構成メモを見返しながら、サビにつながる流れを作っていきましょう。
また、1番と2番で視点(自分視点、相手視点)を変えたり、時間軸(過去、未来)を変えたりすると、物語に深みが生まれます。
作詞を始めるときのポイント

作詞をするにあたって、音楽理論の知識や高価な機材は必要なく、「書きたい」という気持ちがあれば、いつでも誰でも始められます。
ここでは、作詞を始めるときのポイントについて解説します。
思いついた表現を書き出す
まず準備したいのが、自分の気持ちを自由に書き出せるノートとペンです。スマートフォンやタブレットのメモアプリでも構いません。
まずは思い付いた言葉や感情、歌詞をその場で残しておける環境を作ることが大切です。
ふとした瞬間に浮かんだフレーズや、日常で感じたことをすぐにメモする習慣を持つことで、作詞に活かせる素材を集められます。
いきなりノートに歌詞を書き始めるのではなく、気軽に思ったことや単語を書き出しておくと、作詞するときのヒントになるでしょう。
さまざまな表現に触れる
作詞を上達させるには、インプットも重要です。好きなアーティストの歌詞を見ながら、「なぜこの言葉が使われているんだろう?」と考えてみましょう。
感動したフレーズや印象に残った表現をメモするだけでも、自分の言葉の引き出しが増えていきます。また、言葉のバリエーションを増やすには、本を読む、辞書を引いてみるなども効果的です。
さらに、ジャンルにこだわらずさまざまな音楽を聴き、幅広い音楽表現を知ることも、表現力アップにつながるでしょう。
作詞が楽しくなる3つのコツ

作詞のステップと基本的な考え方を身に付けたら、次は自分らしい表現にチャレンジしてみましょう。
ここでは初心者がワンランク上の作詞を目指すための、楽しく取り組める3つのテクニックを紹介します。
韻を踏んでみる(ライミング)
韻を踏むことで、歌詞にリズムやまとまりが生まれ、聴いていて心地良い印象を与えられます。
例えば、「世界(sekai)」と「未来(mirai)」のように、語尾の音(-ai)をそろえるだけでも良いでしょう。
難しく考えず、言葉遊びのような感覚で楽しみながら取り入れるのがコツです。
比喩(ひゆ)を使ってみる
比喩とは、あるものを別のもので例える表現のテクニックです。
例えば「君の笑顔は太陽のようだ」といったように、抽象的な感情を分かりやすく伝えるのに役立ちます。
「まるで〜みたい」「〜のような」などの形を使えば簡単に取り入れられるので、初心者にもおすすめです。
比喩を使うと、聴き手の想像力を刺激し、印象的で心に残る歌詞に仕上がります。自分なりのユニークな比喩を探すのも楽しみの一つです。
五感を意識して情景を描写してみる
感情をよりリアルに伝えるには、「悲しい」「楽しい」といった感情を直接的に表現する言葉だけではなく、具体的な情景を描写することも効果的です。
例えば、悲しみを表現するなら「冷たい雨が窓を叩く」と描写することで、読者はより深く悲しみを想像することができます。
五感を意識して言葉を選ぶと、読み手の心に響く表現が生まれやすくなるでしょう。
専門的な作詞・作曲はテアトルアカデミーで学ぼう

印象に残る楽曲を作るには、感性だけでなく音楽理論の知識もあると、大きな助けとなるでしょう。
テアトルアカデミーの「ON-LABO」では、楽譜の読み方や音階、コード進行をはじめとした基礎的な音楽理論を丁寧に学べます。
歌詞と調和するメロディーを合わせることで、より楽曲の表現も豊かになるでしょう。
中学生〜30歳向けの「ON-LABO」、31歳以上向けの「Music100」の2コースがあり、年齢やスキルに応じて学べるのも魅力です。
作詞・作曲だけでなく、DTM(デスクトップミュージック)や楽器演奏など、実践的なスキルも身に付くため、楽曲制作を1人でできるようにもなるでしょう。趣味としてはもちろん、将来的に音楽活動を目指したい方にもおすすめです。
テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!
- 実力派の役者が所属する芸能事務所に入りたい
- 大手メディアへの出演実績が豊富な芸能事務所に入りたい
- 芸能活動に向けた本格的なレッスンを受けたい
作詞は中学生からでも楽しく始められる!

作詞は、特別な知識や道具がなくても誰でも始められる表現方法です。まずはテーマを決めて、物語を構成しながら言葉を集めていくことで、自分だけの歌詞が生まれます。
恋愛や悩み、夢、架空の世界など、テーマは自由です。歌詞を通して何を伝えたいか考えながら作詞をしてみましょう。
より良い歌詞を作りたい、本格的に楽曲制作を学びたい方は、テアトルアカデミーの「ON-LABO」がおすすめです。
基礎的な音楽理論を学びながら、より深く印象的な作詞・作曲ができるようになるでしょう。
DTMや楽器演奏など、専門的なスキルをプロから学べる環境が整っています。
まずはオーディションにエントリーして、将来の夢への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
テアトルアカデミーはこんな方におすすめ!
- 実力派の役者が所属する芸能事務所に入りたい
- 大手メディアへの出演実績が豊富な芸能事務所に入りたい
- 芸能活動に向けた本格的なレッスンを受けたい